植物工場とは?
メリット・デメリット 導入のポイントを解説
本記事では、植物工場の概要やメリット・デメリット、導入時のポイントを解説します。
作物栽培方法の見直し・農業への参入などをご検討の方はぜひご覧ください。
植物工場とは
植物工場とは、人工的に制御された環境下で植物を栽培する施設のことです。光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養液などをコントロールし、計画的かつ安定的に植物が生育できる環境を整えることができるのが特徴です。
外部の自然光を使わず、すべてを人工環境で制御する「完全閉鎖型」と、自然光も利用しながら補助的に人工環境を使用する「半閉鎖型」があります。
近年、気候変動による豪雨や猛暑、干ばつなどの影響により、農作物が被害を受けるケースが多く見られますが、植物工場は自然災害による被害を受けにくいため、気候変動に対応した次世代の農業インフラとして注目されています。
植物工場は宇宙開発にも取り入れられているほか、小さなスペースで大量の栽培が可能なことから、将来的な食糧問題にも対応可能です。
植物工場のメリット
植物工場には以下のようなメリットがあります。
天候や季節に左右されず年間を通して栽培できる
植物工場では、温度、湿度、光量などの環境を人工的にコントロールするため、天候や季節に関係なく作物を栽培できます。このため、台風や冷夏、干ばつ、日照不足、霜などの自然災害・天候不順の影響を受けることがなく、安定した生産が可能です。
また、周年栽培が可能なため、供給量を一定に保つことができ、食料不足のリスクを軽減します。
計画に沿って安定した栽培ができる
植物工場では、環境を完全に制御できるため、収穫量や品質を予測しやすく、計画的な生産が可能です。需要に合わせて供給をコントロールすることで農産物の価格を安定させることができ、消費者や生産者双方にとってメリットがあります。
収穫スケジュールを管理することで、毎日一定量の農産物を出荷することも可能です。
連作障害が発生せず短期間で栽培できる
植物工場では土を使用せず、養液栽培(水耕栽培)を採用しているため、連作障害が発生しません。さらに、光や養分を最適化することで成長速度を速め、短期間で収穫可能な状態に育てることができます。
例えばレタス類では、土耕栽培の場合は年間で1〜3作が一般的ですが、植物工場なら年間10作以上の栽培が可能です。
無農薬野菜を栽培できる
閉鎖された環境で栽培を行うため、病害虫の侵入を防ぎ、農薬を使用せずに野菜を栽培できます。これにより、消費者に安全で安心な食材を提供できるほか、洗浄の手間や水道費の削減にもつながります。
近年は安心・安全な農作物に対する消費者のニーズが高まっているため、そうしたニーズに対応できる点は大きなメリットと言えます。
高機能野菜を栽培できる
光の種類や養液などの成分を調整することで、栄養価や機能性を高めた野菜を栽培することが可能です。例えば、ビタミンや鉄分が豊富な野菜、抗酸化作用の強い野菜など、健康志向の高い消費者のニーズに応える作物を生産できます。
こうした高付加価値な野菜は一般的な野菜よりも高い値段で販売できるため、収益性の向上にも貢献します。
従来農業に適していない土地でも栽培できる
農業は一般的に広い土地が必要ですが、植物工場は都市部や狭い土地でも導入でき、効率的な土地利用が可能です。多段式の棚を利用することで、限られたスペースでも高い生産性を実現できます。一軒家や事務所の空きスペースがあれば、一定の収量を確保できる点は大きな魅力です。
これにより、都市部での食料自給率向上や輸送コストの削減が期待されます。
作業のマニュアル化が可能なため誰でも栽培できる
屋外での栽培は、雨量や日照量などの環境が日々変化するため、水量や肥料の量の調整などが属人化し、マニュアル化が難しい課題があります。
一方で、植物工場は自然環境に左右されにくいため、栽培方法や作業内容を標準化・マニュアル化することが可能です。これにより、農業経験のない人でも作業ができるほか、高齢者や障害者の雇用促進にもつながります。また、ICT技術を活用した自動化により、作業負担を軽減しつつ効率的に生産できます。
植物工場のデメリット
植物工場は多くのメリットを持つ一方で、導入や運営においていくつかの課題があります。
初期費用やランニングコストが高額
工場の建設費、土地の確保、設備投資(照明、空調、ICT制御システムなど)などの初期費用が必要であり、数億円規模のコストがかかる場合があります。
また、照明や空調設備を常時稼働させるため、光熱費をはじめとするランニングコストの負担も大きくなります。
これらのコスト負担は、特に中小企業にとって大きな障壁となり、収益化までの期間が長くなることも課題です。
栽培可能な作物が限定的
通常の農業と比較して、栽培できる作物の選択肢が限られます。
例えば、葉物野菜(レタス、サラダ菜、小松菜など)や、一部のハーブ類、果菜類(トマト、イチゴなど)は栽培可能ですが、背丈が高い作物や根菜類は生産が難しい場合があります。
IT技術の知識が必要
植物工場の運営には、IT技術の活用が不可欠です。特に温度、湿度、光量、養液などの栽培環境の管理や機械の操作において、ICTや自動化技術に関する知識が求められます。
また、技術的に未確立な部分もあり、最適な環境制御や作物の生育特性に関する知見が十分に蓄積されていない点も課題です。
植物工場導入のポイント
以下では、植物工場を導入する際のポイントをケース別にご紹介します。
作物栽培方法を変更する場合
露地栽培やハウス栽培とは異なり、環境を人工的に管理するため、作物ごとに最適な設備やスペースが必要です。例えば、葉物野菜と果菜類では必要な光量や栽培棚の高さ、水耕装置の構造などが大きく異なります。
したがって、栽培したい作物が工場内の環境に適応できるかを事前に検討し、作物に合わせたスペースや装置の導入が可能か確認することが重要です。既存設備の転用の可否もポイントになります。
新規ビジネス参入の場合
前述の通り、植物工場には多くの初期投資費用やランニングコストがかかります。
そのため、年間の収穫量と単価から売上を予測することはもちろん、設備費、人件費、光熱費などの支出の見積もりを行い、投資回収期間と利益率を試算し、事業として成立するか検討することが重要です。
販売先(飲食店、スーパー、加工業者など)や需要動向をあらかじめリサーチし、安定した販売チャネルを確保することも成功のカギを握ります。
福利厚生の場合
企業や施設での福利厚生目的の植物工場では、必ずしも高い生産性や採算性を求める必要はありません。ただし、設置場所や導入すべき設備をしっかりと検討する必要はあります。
例えば、「建物内や敷地内に安全に設置できるスペースがあるか」「導入したい作物に合わせた小型・簡易な設備で運用できるか」といった点を事前に検討しておきましょう。
加えて、社内のコミュニケーション活性化やSDGs対応のアピールにもつながることから、PR戦略もあわせて検討すると効果的です。
植物工場は正和工業のZEUS INBESTにご相談ください
植物工場は、安定した食料供給や環境負荷の軽減を実現するだけでなく、都市部での農業や高機能野菜の生産など、従来の農業では難しかった課題を解決する可能性を秘めています。一方で、初期投資やランニングコストなどの費用面や、IT知識の獲得と運用といった課題をクリアする必要はあります。
特に採算性を考えると、土地や工場をリーズナブルに購入することが重要です。
「ZEUS INBEST」は、工場・倉庫を中心として取り扱う不動産仲介サービスです。
建設ベースの不動産だからこそわかる各物件の正確な状態や懸念点もお伝えすることで、安心・適切な物件購入をサポートします。物件の購入からリノベーション・管理までワンストップで提供できるので、検討時点でリノベーション費・諸経費込みの投資費用を算出することが可能です。
植物工場にも活用できる物件の購入にご関心のある方は、下記よりお問合せください。
お役立ち資料

関連コラム
このコラムを書いたライター
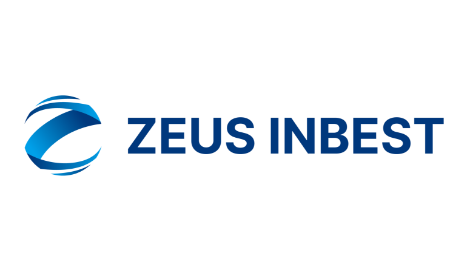
培った技術力・ノウハウを活かし、不動産仲介サービス「ZEUS INBEST」を通して物件に関する情報提供から管理・リノベーションまでサポートいたします。
コラムにて物件売買に役立つ様々な情報を紹介しています。


